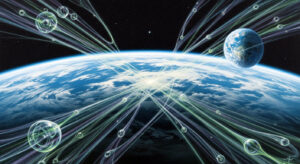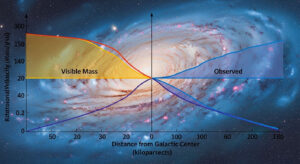私たちは、宇宙を観測する存在である。
けれどももし、宇宙そのものが“自分を観測する”瞬間を迎えるとしたら――?
天文学と量子論の狭間では、長くひとつの問いが議論されている。
それは「観測が現実を定義する」という原理。
もしこの理屈が真実なら、宇宙の誕生以来、宇宙は“観測者”を待っていたことになる。
そして、私たちの存在はその“観測の完成形”に近づいているのかもしれない。
観測という行為の謎
量子物理学によれば、粒子は観測されるまで「状態が決まらない」。
電子は波であり、同時に粒でもある。
この曖昧さを収束させるのが“観測”であり、世界はその瞬間に形を持つ。
ならば宇宙規模でも、同じことが起きているのだろうか。
銀河の光が人間の眼に届いた瞬間、宇宙は自らを確定させている。
観測者とは、宇宙が自分の存在を確かめるために生み出した“鏡”なのかもしれない。

意識と宇宙の共鳴
近年、神経科学と宇宙論の交差点で注目されるのが「宇宙的意識仮説」。
人間の脳の構造は、宇宙の大規模構造(銀河ネットワーク)と驚くほど似ている。
枝分かれする神経網と、銀河団をつなぐフィラメント。
その相似は単なる偶然ではないとする説がある。
私たちの意識が宇宙を観測するのではなく、宇宙が自らを意識するために“私たちを通して見ている”としたら――。
この世界のすべての知覚は、宇宙が“自分を思い出す”ためのプロセスにすぎない。

最後の観測者
もし宇宙が自己認識を完成させる時、それは終焉ではなく閉じるループの完結だといわれる。
観測が最大限に達すると、宇宙は“自分というデータ”を読み終え、再び無へと溶けていく。
そして、次の宇宙が生まれる。
その最初の光が新たな観測者を求めて拡がっていく。
つまり、私たちは“観測する者”であると同時に、次の宇宙を生むための視線でもある。

宇宙が自分を見る日
宇宙は冷たく、広く、そして静かだ。
けれども観測が続く限り、そこには意識の火が灯っている。
無数の星々が光を放ち、無数の生命がそれを見上げる。
その行為こそが、宇宙を“生かす”行為なのだろう。
――いつの日か、宇宙は自分を完全に認識する。
そしてその瞬間、私たちという存在の意味も、ひとつの答えになるのかもしれない。